Dr.STONEで千空が作った液晶ディスプレイの考察
先週発売の少年ジャンプ2022年2号の「Dr.STONE」で千空が液晶ディスプレイを作ってました。

半導体が地獄とまで言ってたのになんで液晶ディスプレイを作れるのか?
と思う人がいるかもしれませんが、LCD設計して20年弱の専門家の端くれとして答えると可能です。
ツイッターで軽く考察してたら原作者の稲垣理一郎さんが反応してくれたので調子にのってもう少し考察したくなったのでこの記事を書いております。
ジャンプの巻末コメントでも触れましたが、偏光板の説明は「しなくても本質の理解は変わらない」という理由でカットしてあります。(加えたバージョンは理解が大変難解でした)もちろん作中の千空達は、実際には偏光板も貼っています!考察ありがとうございます!
— 稲垣理一郎(リーチロー)💵🪨🏈 (@reach_ina) December 19, 2021
千空が作った液晶ディスプレイは単純マトリクス方式*1のパネルです。
アラフォーの人なら誰もが一度は見たことがある初代ゲームボーイの液晶ディスプレイと同じ方式です。*2
現代のスマホやTV等に使われているTFT*3を用いたアクティブ・マトリクス方式と違って、
トランジスタ(半導体)が必要ないため、とてもローテクで作成可能なのが特徴です。
どのような構造をしているかというと、シャープがズバリそのものの図を載せてくれてるので引用してみます。

液晶ディスプレイの構造と作り方|液晶の世界:シャープより引用
構成している材料を一つずつ確認していきましょう。
偏光フィルターとは、サングラスにも使用されているものです。
目次コメントにあるように作中では説明が省かれていますが、話を単純化するためには必要な処置だと思います。
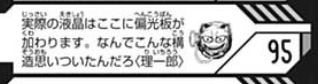
そもそも光とは波の性質を持っており、その波は360度あらゆる方向に振動しているんですが、それを一方向のみ取り出すフィルターです。
「一方向のみ取り出すなら光量が1/360になるんですか?」
と以前後輩に聞かれたことがありますが、そんなわけがありません。
どういう原理かというと波のベクトルで考えたら簡単です。
偏光子が並んだ角度の成分だけ抽出されるので、光量は半分になります。
偏光フィルターの原料は主にヨウ素化合物とPVA*4なので、石油と海藻があれば何とかなるでしょう。
ヨウ素化合物を溶かしたPVAを一方向にぐぐっと伸ばせばヨウ素化合物の方向が揃って、ナノサイズの縦縞模様になり、それが偏光子として仕事をしてくれます。
材料も簡単に手に入るし作り方も単純なため、千空とカセキならすぐに作れると思います。
ただ、これらの説明を入れるなら最低1ページは欲しいところなので、漫画として省くのは正解だと思います。
ガラス基板ですが、完全に平面のガラス基板が必要です。
これを工業的に作ろうとするならかなり大変ですが、実験室レベルならカセキがすぐ作れるのはカメラ作りの時にわかってますね。

透明電極とは可視光を透過する金属で、もっとも一般的なのがITOと呼ばれる金属です。
これはインジウムと錫の合金の酸化物です。
インジウムはレアメタルなので入手が難しいのですがアカシャならありそうですね。
ゼノなら簡単に合金を作ってくれそうです。
配向膜はポリイミドをコットンでこすって作るんですが、千空たちはガラス基板を直接削っているように見えます。
このガラスの溝が配向膜の役割をしているのか、それともガラスに塗っているITOをパターニングしているのかはちょっとわかりません。
単純マトリクス方式とか古すぎる技術なので私も詳しくは知らないのでわからないです。(専門家とは?
液晶は千空が合成してますが、n-ブチルアニリンとメトキシベンズアルデヒドが材料ということはMBBA(4-メトキシベンジリデン-4-ブチルアニリン)だと思います。
おそらく駆動可能な温度範囲を広げるために他の液晶材料との混合物になっているとは思いますが、千空ならそれらも合成して混ぜてるでしょうね。
ちなみになんで電圧をかけると液晶が動くかというとですが…
ディスプレイに使われる液晶は分極している細長い形状のものが使われています。
つまり、長軸方向と単軸方向では誘電率が変わっているのです。
透明電極に挟まれた液晶はキャパシタ(コンデンサ)における誘電体として振る舞うので、電場に従って誘電体として有利な誘電率となるように回転するのです。
キャパシタ(コンデンサ)の誘電体でしかないので交流でも問題ないというか、直流だと液晶が壊れてしまいます。
SHARPが電卓で液晶ディスプレイを実用化した時はこの事実に気付くのに膨大な試行錯誤を要したのですが、千空なら知らないはずがないのでサクっと交流回路を作っていることでしょう。
スペーサーはミクロンサイズですが、カセキなら… カセキならきっと何とかしてくれる…!
カラーフィルターはモノクロ表示の千空たちに不要なので作ってないですね。
バックライトですが、現代ではLEDを使用してますが、一昔前は冷陰極管でした。
ぶっちゃけ光れば豆電球でも問題ないですからこれは7巻の時点で作ってるのでとっくにクリアしています。

それとタッチパネルも作ってましたが、これは抵抗膜式という古くはATMとかでも使われている方式です。
タッチした場所までの抵抗値から距離を算出するシンプルな方式です。
そのため、二点同時タッチすると誤検出してしまうのですが今回は無視で良いでしょう。
厚さが均一のITOを用意する必要がありますが、カセキなら… カセキならきっと何とかしてくれる…!w
もちろん、抵抗値から位置を割り出す演算は必要になりますが、それはパラメトロンでも演算できる範囲でしょう。
つまり、半導体を使わない薄くて軽いタッチパネル付きフラットパネルディスプレイは液晶ディスプレイ一択なのです。
OLEDはTFTがほぼ必須だし、そもそも材料が実験室レベルだと寿命が短すぎですからね。
プラズマディスプレイもミクロン単位の製造技術がないと無理ですし。
という感じで最高に面白いDr.STONEですが、現在DMM電子書籍で50%ポイント還元セール中です。
もしまだ読んでないなら、今から是非とも読もう!
このハーレムエンドがすごい! 2020
みなさんジャンプで12/21発売のジャンプに載っている「ぼくたちは勉強ができない」の最終回を読みましたか?
個別ルートを描いた後に、色々な可能性が感じられる元の時空に戻っての終わり方は良いモノだと思います。
「ゆらぎ荘の幽奈さん」のように個別ルートの未来の可能性を描いた後に超長期の伏線を回収してメインヒロインルートを確定させるのもアリだと思いますが、コレはコレでアリだな、と。
そう深く思っていたんですが…
ふなつかずきさんはそんな私の少年誌的発想力に縛られた思惑を圧倒的に超えてきました…
そう… 12/22に発売されたグランドジャンプむちゃに「すんどめ!! ミルキーウェイ」のANOTHER ENDが最終回を迎えたんですが、これが凄かったのです!!!
そもそも「すんどめ!! ミルキーウェイ」は正ヒロインのルネENDだったわけですが、
その後に増刊のむちゃで各サブヒロインのルートを描くという「ぼくたちは勉強ができない」の先を行っていたんですが、終わり方も先を行ってしまったのです!!!
そう… つまり…!

本当にハーレムエンドを実現しやがったのです!!!!!!!
スゲー! 頭ワリー!(褒めてます
いやいや、現代日本でハーレムとか無理だろ、と思うかもしれませんがご安心ください。
ちゃんと西アフリカに移住していますから!(ちゃんととは
しかも青年誌だからエロシーンがガッツリと描かれているわけです!
いやはや素晴らしい!
こんなハーレムラブコメのエロエンディング、エロゲでしか見たことねえよ!*1
しかし今回は本番シーンが8ページもあったんですが…
今週のYJに「某雑誌はセッ〇スシーン4PまでOK」という表現があるのですが、これは本番シーンが4ページという意味です。ふなつ一輝先生に教えて頂きました。でもこれはふなつ先生限定の話かもしれないと思ったので、石田スイ先生に「ほんと?」って訊いたら「ほんと」って言ってたので多分ほんとです
— 赤坂アカ (@akasaka_aka) February 14, 2019
ヤングジャンプではなくグランドジャンプむちゃだからOKだったのか、それとも編集部に土下座で頼んでみたのか…
まぁ、どちらにしろ読者としてはとても満足なのでOKです!
でも、前みたいにDMM同人で増補版があるともっと満足できると思います!
そんな訳でこのANOTHER END最終回が収録される単行本は2月に発売されるので首を長くして待ちたいと思います。
今ならDMMで既刊も50%ポイント還元で買えるので是非どうぞ…!
*1:エロ漫画は除く
「このライトノベルがすごい! 2021」に協力者として参加しました
今年もやってきましたこの季節。
ただ、例年と違って今年は私が投票したランキングの発表はやりません。
何せ今年から協力者がどれに投票したのか詳らかにされる方針に変わったので。
このブログでそこに言及したらネタバレになってしまうからです。
とはいえ何故、どういった基準で投票したのかは備忘録的に書いておこうと思います。
投票した5作
このラノの読者を「最近出たラノベの中でも面白い作品を読むのに参考にしたい人」と想定したので、基本的に新作から選出しました。
長期シリーズが面白いのは当たり前なので、「新作の中でもこれが面白いよ!」という青田買い向けの情報の方が求められているのではないかな、と。
1位は単純に私が一番面白いと思ったので。現在は入手難易度は跳ね上がったけど、電子書籍では出し直されたみたいなのでそちらで購入して欲しいですね。
2位も単純に面白く、これから更に面白さが増しそうだと思ったので。非常にメディアミックス向いている作品なのでこれからが楽しみなので、青田買いするなら今でしょう。
3位はWeb版を何度も読み返しているので単純に1巻だけの評価とは言えないのは申し訳ないです。でも、Web版読んでるからこそ期待値はかなり高いと確信しています。
4位は個人的に刺さりまくったので。1,2巻とも読んでて泣いてしまったので、自分に嘘はつきたくないので入れました。
5位は作者の今までの実績を込みでの評価です。天国大魔境みたいなもんですね。
イラストレーター
どうしても実績と実力がある人を選んでしまい、新人さんを選びにくいです。
選考基準としては「モノクロも上手いこと」を重視しています。
男キャラ・女キャラ
これは新作ではなく既存作品からもチョイスしています。
このランキングは読者にとって知らないキャラよりも知っているキャラが出た方が読んでて嬉しいと思うので。
あと、単純に既刊が多いほどキャラに深みが出てきて魅力を感じるってのもあります。
惜しくも選外にした作品
「超高度かわいい諜報戦」結構面白かったんですけど、今のところ続刊がない悲しみ…
「エリスの聖杯」綺麗に完結して素晴らしかったですね。もう一つ枠があれば間違いなく入れてました。
エロゲと少年漫画とラブコメと
ご注意:この記事には「五等分の花嫁」と「ぼくたちは勉強ができない」のネタバレが含まれますので単行本派の人はご注意ください。
「ラブひな」とは

赤松健が「AIが止まらない」完結後に満を持して週マガに帰還して連載を開始したラブコメ作品。
今となっては意外かも知れませんが「ラブひな」はヤンキー漫画全盛だった週マガをオタク向けへとシフトさせた恐ろしい作品なのです。
現在はマンガ図書館Zで全巻読めますがざっくり説明すると…
「大きくなったらふたりでいっしょにトーダイ行こーね」と約束をした幼馴染みと再会するため、多浪をする浦島景太郎が祖母が経営する旅館に住み込みに行ったら女子寮になってて管理人をやりながら同居する女の子たちとラブコメしつつ東大を目指す物語です。
当時のオタクの人たちはみんな思いました。
「とらハ2」じゃねーか! と。
(※ブコメで指摘されましたがとらハ2はラブひなより後でした。私の記憶間違いでした、すみません)
エロゲのとらハシリーズ*1を即座に連想するくらいにエロゲ、ギャルゲ要素がてんこ盛りなんですが、エロゲ要素を少年漫画に輸入するのは当時はとても画期的だったのです。
ちなみにこの作品は終盤でメインヒロインの成瀬川なるは「自分は約束した幼馴染みではないかも…」と思いグダグダするんだけど、景太郎は「思い出の女の子じゃなくても成瀬川のことが好き」と言ってくれるんですよね。

つまり「景太郎が選んだ女の子がたまたま約束した幼馴染みだった」という構成なわけです。
「五等分の花嫁」とは
赤松健のもう一つの代表作「魔法先生ネギま!」の主人公、ネギ=スプリングフィールドからPNを取ったくらいに赤松健ファンな春場ねぎさんが週マガで連載したラブコメ作品。
瀬尾公治と流石景が捻じ曲げてしまった週マガ的ラブコメを、元の赤松健的なものに戻した作品でもあります。
今更説明する必要もないと思いますが、貧乏苦学生の上杉風太郎が父親が見付けてきた家庭教師のバイト先が五つ子だったことから始まるラブコメです。
ただ、選んだヒロインの結婚式の回想から始まるというのは斬新でしたね。

読めばわかるんですが、選ばれるヒロインは初めから伏線が張り巡らされており、丁寧に読み取っていけばわかるんですよね。
「魔法先生ネギま!」も「UQ HOLDER!」で答え合わせされる前にガチファンの間では千雨が選ばれたことがほぼ確定情報として扱われてましたが、同じように理詰めでわかるのです。
ラブコメとしての面白さがあるのはもちろんなのですが、ミステリー要素も強かったように思えます。
ちなみに主人公の風太郎と五つ子の一人である四葉は小学生の頃に修学旅行先の京都で出会っている「思い出の幼馴染み」なんですが、それが決め手となったわけではありません。
この作品も「風太郎が選んだ女の子がたまたま約束した幼馴染みだった」という構成なわけです。
ここにも赤松健の遺伝子が感じられますね。*2
「ニセコイ」とは
キムチ。
かつてヤマカムの山田さんは言いました。
「『ニセコイ』はジャンプ史上最長連載のラブコメだから一番面白いに決まっている! Q.E.D.!」
と。

そうだね、一番面白いに決まってるよね!(棒
この作品のアレっぷりは指摘してたら終わらないくらいにアレなんですが、結局のところは主人公がクソだったというのが一番なんですが、
「どれだけ他のヒロインが好感度を上げても『約束された勝利の幼馴染み(エクスカリバー)』にはかなわない」と読者に感じさせる構成のクソさが最悪でした。
私は観てないですけど、実写劇場版はそこが改善されて面白かったらしいですね。
私は観る気ないんですけども。
「ぼくたちは勉強ができない」とは
「ニセコイ」のスピンオフ「マジカルパティシエ小咲ちゃん!!」を描いていた筒井大志さんが週ジャンで連載しているラブコメ作品。
古味直志が破壊した週ジャンのラブコメを再構築した作品でもあります。
今更説明する必要もないと思いますが、貧乏苦学生の唯我成幸が推薦枠確保のため同級生の家庭教師をすることから始まるラブコメです。
一応言っておくと「五等分の花嫁」より半年ほど始まるのが早いです、念の為。
二人のヒロインから始まった作品ですが、ハーレムラブコメとしては当たり前なんですがヒロインが増えていき最終的に5人になったんですが、人気投票では大方の予想を裏切り桐須真冬先生が不動の一位でした。

これを見てかつてヤマカムの山田さんは言いました。
「『ぼくたちは勉強ができない』というタイトルなんだから教師がヒロインなのはおかしい! 怠慢教師勉強できるじゃん! はい論破!」
と。

「『桐須先生は家庭科ができない』だよ」と指摘したらぐうの音も出なかった模様。
現代を舞台にしたラブコメ作品だし一人しか選ばれないのは仕方がないのですが、昨年末からの本誌連載でうるかルートに入っていて少数のうるかファン以外が困惑したんですよね。
しかも決め手となったのが過去に成幸を救っていたエピソードを土壇場で出してくるという「どれだけ他のヒロインが好感度を上げても因果を逆転してしまう『斬り抉る戦神の幼馴染み(フラガラック)』にはかなわない」な構成には思いっきり失望しました。
お前、「ニセコイ」からなんも成長しとらんやんけ! と。
ジャンプ作品から学ぶなら「すんどめ!! ミルキーウェイ」みたいにアナザーエンドを描いてマルチエンド化しろと!
同じ集英社だとライトノベルだと「ベン・トー」なんかもっと前に12巻でマルチエンドしてたんだぞ!
特にメインヒロインの槍水先輩を差し置いて一番人気の著莪なんてエロ展開もあるくらいなんやぞ!
と、憤懣やるかたなく思ってたんですが…

「ぼく勉」パラレルストーリー、開幕!
やったのか!! 筒井大志!!
赤松健が取り入れたエロゲ要素をここに花開かせるのか、筒井大志!!!
おい……見てるか赤松健……
お前を超える逸材がここにいるのだ……!!
それも……2人も同時にだ………
赤松健……
*1:のちにスピンオフで誕生するのが「魔法少女リリカルなのは」
「このライトノベルがすごい! 2020」に協力者として参加しました。
今年もお呼ばれしたので参加させて頂きました。
月に5~10冊ほどしか読んでない私が協力者などと烏滸がましいと思うのですが…
FGOとかダンメモとかソシャゲが忙しいんだよね…!
さて、このラノは誰が何に投票したのかわからないので今年もメモとして残しておきます。
作品部門
- りゅうおうのおしごと!
- ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 外伝ソード・オラトリア
- 本好きの下剋上 ~司書になるためには手段を選んでいられません~
- 西野 ~学内カースト最下位にして異能世界最強の少年~
- 14歳とイラストレーター
- 無職騎士の英雄譚
- ひげを剃る。そして女子高生を拾う。
- 噂の学園一美少女な先輩がモブの俺に惚れてるって、これなんのバグですか?
- 陶都物語 ~赤き炎の中に~
- スレイヤーズ
今年は部門を分けずに投票、ということでこの様になりました。
「りゅうおうのおしごと!」は文句なしで1位に投票。
「ダンまち」は本編と外伝どちらも面白かったんですが、どちらも入れるのはどうかと思ったので、区切りがついてベルくんの見せ場で鳥肌が立ったソード・オラトリアに投票しました。
「本好きの下剋上」は今年も面白すぎたので入れざるを得ない…!
「西野」「14歳とイラストレーター」「ひげを剃る。そして女子高生を拾う。」「噂の学園一美少女な先輩がモブの俺に惚れてるって、これなんのバグですか?」は一応ここ1,2年の作品から選出しました。やはり新しい作品を読んで欲しいですし。
そう言いながら「スレイヤーズ」を選ぶのは… すみません、私のわがままです。だって、やっぱり面白かったんだもん…!
イラストレーター部門
- しらび
- 西沢5㍉
- たかやKi
しらびさんは「りゅうおうのおしごと!」であそこまでのイラストを見せられたらぶっちぎりで1位に選んでしまいます。
西沢5㍉さんは美少女の美少女っぷりが素敵だよね。
たかやKiさんはね… エッチすぎる美少女が素敵なのでね…!
男性キャラ部門
ロリコン八一は何だかんだで良い主人公なのでね…
不屈のレイはその生き様というか、そういうのがカッコイイな、と。
ベルくんとどちらを2位にするか悩んだけど、作品部門でインフィニット・デンドログラムを選ばなかったのでキャラ部門くらいは譲ろうかな、という感じでこの順位になりました。
”今”私にきているマンガ大賞2019 Webマンガ部門
[はじめに]
昨今はWeb漫画やアプリ漫画がめちゃくちゃ増えたんですけど漫画好きでも全部追いきれてない思います。
そこで、ここ1,2年で始まったWeb連載漫画orアプリ連載漫画の中で私が面白いと思う作品を選びました。*1
念の為すでにメジャーになっている作品もピックアップしましたが、この記事の本題はそれ以外の作品です。
[エントリー作品]
■メジャー作品部門
漫画好きでこの作品を知らない人はいないだろうってレベルの作品です。

ハルヒの同人時代から知っている人も多い、殆ど死んでいるのほとんさんの作品。
タイトルから異世界転生モノと勘違いする人が多いですが、基本的にSEGAオタクの痛い漫画です。(偏見
異世界帰りのおじさんのフラグクラッシャーっぷりに悶え、ツンデレエルフさんの健気さも悶えよう!
あと、藤宮さんも可愛いしおっぱい大きくて良いと思う。

陰キャ中二病主人公・市川が天然読モのヒロイン山田に惚れていく物語です。
はじめは市川のことを全然気にしてなかったのに、自分のことを不器用ながら守ろうとしてくれる市川のことをだんだんと気にかけるようになってくる山田に胸キュンが止まりません。
10年前の私に「『みつどもえ』の作者が描く青春ラブコメに萌え殺されるよ?」と言っても間違いなく信じないでしょう。
ちなみに作者twitterでのみ公開中の番外編もめっちゃくちゃ萌えます。
Twitter用に描いている漫画をまとめました。
— 桜井のりお@ロ④僕ヤバ①発売中 (@lovely_pig328) 2019年4月30日
⚡️ "僕の心のヤバイやつ"https://t.co/f4dZ35uubg

既に何冊もエロ同人誌が出るくらいの大人気作品です。
twitter発のラブコメ漫画なんだけど、初期はラブ要素はちょい薄めですが徐々に上がってます。
一番の見所は宇崎のSUGOI DEKAIおっぱいです。(キリッ

ジャンプ+が生み出した異端児にして麒麟児。
ジャンプ本誌で打ち切り喰らいまくった作者がまさかWebで花開くとは…
レモンちゃん恥ずかしい…
■準メジャー作品部門
SNSでのバズってるし知ってる人が多いだろうってレベルの作品です。

スパイが任務達成のために円満な家族を築くために選んだのが偶然にも超能力者の孤児と美人な暗殺者だった…!
設定も面白いし、キャラも面白いし、ストーリーも面白くて最高です。
ジャンプ+の新しい看板作品になりえるレベルの面白さだと思います。

(売り上げ的に)世界的にも大人気のソシャゲFGOのエピソードの一つである英霊剣豪七番勝負のコミカライズです。
「圧倒的な画力でぶん殴ってきたぞ!」って感じですね!
おそらくこの画力に対抗できるFGOコミカライズは少年エースで新宿編を描いている佐々木少年さんくらいだと思います。
ちなみにこのコミカライズ、珍しく主人公がぐだここと、女性主人公です。
女性主人公のFGOコミカライズってリヨ版以外なかったかもしれない…

海外のノーベル文学賞受賞作家スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの代表作のコミカライズという、その発想はなかった的な作品です。
作画担当は「狼と香辛料」で一躍知名度を上げた小梅けいとさん。
「狼と香辛料」は英語版出てたしこちらも英語版を出そうと思えば出せるはずなので頑張ってほしいですね。
問題は連載しているのがComicWalkerなところでしょうか。
アプリ無くなっちゃったからブラウザ視聴のみなのがちょっとハードル高いかもしれません。(最近の人はアプリからじゃないと読まない人がわりといる
■コミカライズ作品部門
なろう作品のコミカライズがとにかく多いです。
原作よりも面白い作品もチラホラあります。
たいていはニコニコ静画でも読めます。(多少掲載は遅れますが

近未来に彗星の如く現れたVRMMOインフィニット・デンドログラムで主人公レイ・スターリングが活躍する冒険活劇です。
作品内容的にはSAOというよりもHUNTER×HUNTERのグリードアイランド編が一番近いんじゃないでしょうか。
作画担当はウルジャンでNEEDLESSを描いていた今井神さん。
漫画的な魅せ方がとても上手くてバトルが盛り上がりまくりです。

夢の世界でエルフの仲間と冒険していたつもりが、どうやら本当に異世界だったらしく、
ドラゴンに殺されたと思ったら翌朝隣には仲間のエルフが裸で眠っていて… という話です。
日本の品々に驚くエルフさんが可愛いです。
作画担当の青乃下さんはFGOのメイヴが大好きな人で有名ですね!

GAノベル原作のタイトル通り、純朴な少年による無自覚な俺TUEEEコメディです。
ロイドくんの影響で色々な人が大変な目にあうのが楽しい漫画です。
作画担当の臥待始さんは禁書目録での漫画も描いていたことがあるみたいですね。

神様に俺TUEEEを頼んだら仙人の元で500年修行を積まされたでござる。
仙術と剣術だけでどんな強敵もあっさり倒してしまうので地味なんだけど最強です。
地味に長い原作を圧縮してサクサクみせてくれることに期待…!

今をときめく(?)幻冬舎のWeb漫画サイトcomicブーストで連載の本作。
作画担当は主に4コマ漫画を描いてた森ゆきなつさんです。
絵柄も可愛いし読みやすいし可愛いし面白いんだけど、わりとスローペースなのがちょっと心配かも。

たまたま精製に成功した不老の秘薬のお蔭で、才能がないながらも5000年間引きこもって地道に魔法の研究をしていたアズリー
使い魔のポチに促されて外に出たアズリーが人々と出会い、成長していく物語です。
作画担当はわりとコアなファンが多い荒木風羽さん。
コミカライズに伴い副題に昇格したポチがわりと可愛らしいです。

現代日本で病気の末に死んだ主人公のヒラクが神様に望んだのは俺TUEEEではなくて健康な身体と農業ができる環境。
異世界で死の森と恐れられる地で開墾して農作物を作り、村となっていって…
作画担当はラノベのイラスト経験もあり、ハーレムラブコメやコミカライズも経験がある剣康之さん。
作風にも合っててとても面白いです。
原作以上にヒロインの可愛さがビンビンと伝わってきて素敵です。
ハクレン可愛い。

タイトルの通り、14歳コスプレイヤーJCにお世話されるイラストレーター青年の業界モノのコミカライズです。
MF文庫Jの原作よりもエロ成分多めでお送りしております。
ちなみに原作者は以前TVアニメ化した「異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術」のむらさきゆきやさんです。
原作から無駄な毒を削ってるし、このコミカライズだけ読んだ方がストレスは低いと思います。
■オリジナル作品部門
面白い作品が多いんだけど、連載媒体がマイナーすぎるのがツラい…

ドハマりしているアニメの二次創作イラストを描くミスミさんと、そのミスミさんの絵が性癖にどストライクのアイさん。
SNS上でのみ交流があった二人が即売会で出会ったことで、お互いがJKとOLなのを知ったんだけどJKのミスミさんが積極的にグイグイきて…
タイトル通りの作品で、とても面白いのですがtwitter発とはいえ連載がヒーローズのWeb媒体ということで知名度はイマイチなのが悲しい…
作者のさとさんは元々「いわせてみてえもんだ」というWeb漫画からデビューした方だし、今度「フラグタイム」がアニメ化されるし知っている人も多いのではないでしょうか。
エロ漫画家のちゅぴまろさんと絵柄がそっくりなのは大人たちの秘密だよ!

美人の新任養護教諭のお姉さんはガチオタだったでござる…
好きなことに対しては饒舌になってしまう先生は可愛いし、日々の過ごし方も共感が半端ないです。
架空のソシャゲだけでなく、FGOが伏せ字なしで出てきてシナリオの尊さを興奮して語ってたのには笑いました。
中高生の頃にこんなお姉さんと親しくなりたいだけの人生だった…

おませな小学生の姫乃ちゃんはクラスメイトのオージくんの恋人気分だけど、オージくんは恋愛回路未実装なのである!
空回ってるけど噛み合ってて、ちょっとラブコメるところが面白いです。
それ町のエビちゃんとタケルを想像するとわかりやすいですね。
ちなみに作者のゆずチリさんは元・東大生ということでも有名。

社会に出てもぼっちなみどりさんが、中学時代の唯一の親友であるつぐみちゃんの訃報を聞いて帰省したら、そこにはつぐみちゃんと瓜二つの春子ちゃんがいて…
年の差の百合、というか…
同居モノで百合っぽいんだけど、ただの百合じゃないですね。
とてもエモく、とても不思議な感触の作品です。
実に… 良い…

ドルオタ中学生がある朝目覚めたら美少女になっていたので、憧れのアイドルグループに入ってトップアイドルを目指す物語です。
「君の名は。」以降お馴染みの性転換モノですが、アイドルモノとして意外なほどによく出来ています。
元々ニコニコ静画のアマチュア作品だったのがマンガボックスの編集にスカウトされた、という作品なんですが現在打ち切りの危機!
なんとか続いて欲しい…

巨乳の女の子たちの悩みと、その恋人の穏やかな日常漫画です。
巨乳は太って見えると聞くし、ブラとかも種類が少ないとは言いますが本当に大変なんですね…
でもまぁ、申し訳ないけど、とても眼福だったりするわけです、ハイ。

「都立水商!」の猪熊しのぶさんの最新作ですが、なろう(ノクターン)コミカライズではありません。
でもまぁ、中身は「異世界居酒屋のぶ」や「異世界食堂」のソープランド版と言って差し支えないのではないでしょうか。
「都立水商!」で磨き抜かれた水商売のエロさを120%発揮した素晴らしい内容です。
いやー、本当に素晴らしいくらいに清々しいエロですね!

妖怪ホイホイでバイトにクビになりまくるひのちゃんが先輩のツテで入ったバイト先は妖怪御用達の居酒屋だったでござる。
艦これの同人誌界隈で名を馳せるnoncoさんが何故かマガポケでオリジナル漫画を連載はじめた時は「どういうことなの?」状態でした。
絵柄がエロ可愛いし、同人誌と同じハチャメチャ具合が楽しいよ!

近代麻雀の問題作、一八先生は単行本が出ないというか出せないのでWebで毎週公開されているのだ…!
SNSでもあまりの絵柄のイタコっぷりが度々話題になっていますが、それが高じて本家で仕事するくらいになった錦ソクラさんは凄いと思います。
絵柄だけじゃなくてコマ割りまでキッチリとコピーしてくるのは地味に凄いよね…
それにしても単行本出ないということは印税入らないといことで…
代わりにWeb広告収入が入ってたりするのかな…?
*1:1,2年というくくりから残念ながらわたモテは除外します
ダンメモのすゝめ
ダンメモとは?
劇場版とTVアニメ2期が決定した大人気ライトノベル「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか」
そのスマホ向けソーシャルゲーム「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか メモリア・フレーゼ」の略です。
ダンまちのゲームは色々と出てますが、私はこれが一番好きです。
原作有りのゲームなので敬遠する人もいるかもしれませんが、原作を読んでなくても問題ありません。
もっと言えば、コミカライズ版もアニメ版も見てなくても大丈夫です。
何故ならアニメ版の素材を使ったストーリーパートがアニメ版とほぼ同じ内容だからです。
そう、つまりのこのゲームはコミカライズ版、アニメ版と同じで原作のストーリーを別メディアで展開しているメディアミックス作品なのです!
なので、原作を全く知らなくても楽しめますし、ここからダンまちにハマるのも大いに有りなのです。
ゲームの内容
基本的には「ガチャで出てきたキャラを育成してバトルする」というものです。
私はゲームのジャンルに詳しくはないけどADVRPGとかそんな感じでしょうか?
聞くところによるとゲーム製作を担当しているWright Flyer Studiosが作っているアナザーエデンに近いシステムらしいです。
私はアナザーエデンをプレイしたことがないので聞きかじりになりますが。
リリースからもうすぐ一周年という現在、コンテンツもほぼ解放されました。
大まかには以下のようなコンテンツに分かれてます。
- 冒険
- アニメ準拠のストーリーパート、ゲームオリジナルのイベントストーリーパート、装備用素材集めの迷宮探索等。
- 交流
- キャラクターとの交流ストーリーや個別の冒険パート。全てゲームオリジナル。
- 闘技場
- 原作と同じように難敵を倒していく”怪物祭”とPvPである”戦争遊戯”そして都市最強のオッタルに挑む”栄光挑戦”
アニメ準拠のストーリーパート以外のシナリオはゲームオリジナルなんですが、これの出来が凄く良いんですよね。
原作の設定をちゃんと踏まえた上で出来上がっているリスペクトが感じられる内容なので、原作ファンとしてとても満足がいく出来になっています。
デキの良い公式コミックアンソロジー集を読んだ時の満足感に近いですね。
それもこれもライターさんの力量と原作の大森さんの監修力のお陰でしょう。
まぁ、監修作業が膨大なせいなのか原作の刊行が5ヶ月延期したのは辛かったですが…(笑
キャラの育成
まず、基本的なことですが…
- キャラには冒険者とアシストの2通りがあるが育成方法は共通。
- レベルはバトルをするか経験値アップアイテムで上昇。
- ステータスアップ用素材*1を使い、ステータスを全て解放できたらレベル上限解放。
- ただしデフォルトのレベル上限はレア度に関係なく60。
- 上限を引き上げる限界突破には絆*2が必要。
- 限界突破一回でレベル上限が4ずつ解放され、それが5回できる。
- つまり最大レベル80にするまでに原則的に同じカードが6枚必要。
- それとは別に親愛度のCP Lvが設定されており、それによってステータスが微増。
現在はLv1の状態で☆4がSSRです。FGOとは違うのでたまに混乱します。
排出率もそこそこ高いですが、それでもSSRの数がポンポン増えていくので合計6枚というのは中々に鬼畜です。
実用的にはSSRだとLv.72以上が欲しいところですが、無課金だと半年以上地道にプレイしたら何とかと行ったところでしょうか。
それとFGOと異なり低レアはマジで使いみちがないです。
SRのLv.80で実用になるレベルなんだけど、それでもSSRのLv.72よりも弱かったりするからちょっと辛い…
でも、FGOと違ってほぼ全てのキャラは低レアにもいるんですよね。
いないのはイベント限定のキノの旅のキャラとか、オッタルとか極一部じゃないでしょうか。
だからキャラクターの○○が好き! という人には優しいのではないでしょうか。
そこらへんはデレステに近いかな?
ガチャと課金の仕様
とても優しいです。
FGOをやってる身としてはこれほど優しくて大丈夫なのか心配になるレベルです。
どれくらい優しいかというと…
- FGOの呼符みたいなチケットもあるんだけど、R以上確定、SR以上確定のチケットはイベント等でも簡単に手に入る上にそれでSSRがポンポンでる。
- 連続ログイン30日毎にSSR確定チケットがもらえる。
- イベントを複数繰り返したりしたら限界突破用アイテム*3も手に入れられる。
- 課金も連続ログインが必要だけど30日840円微課金のお得プランもある。
限界突破が必要なゲーム仕様だとはいえ、ここまで楽で良いのだろうか…
無課金でも計画的な石運用でガチでやりこめば上位1万人に簡単に食い込めちゃいます。
ユーザー数が少ないことはないと思うし、実際北米だと日本の4割増しで売れる大ヒットしてるみたいなんだけど、案外エンジョイ勢が多いのかな?
好きなところ
- ゲームオリジナルのシナリオが面白い。
- アニャクロ探偵が特に良い!
- シナリオの原作リスペクト度が高い。
- ゲーム内用語も原作リスペクト度が高い。
- SDキャラの動きが可愛い。
- ほぼフルボイス。
- バトルが難しすぎない。
色々とありますが、やはり私が一番気に入っているのは原作への強いリスペクトが感じられるという所ですね。
それが随所に感じられるから、ゲームオリジナルシナリオで多少はっちゃけても笑って許してしまうわけです。
「私立オラリオ学園」とかはっちゃけすぎだと思うけど、私は凄く楽しめました。(笑


































